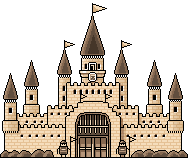<ぶらり坂本>
<西教寺>
西教寺は、天台真盛宗の総本山。
正式名を戒光山兼法勝西教寺。
聖徳太子が恩師である高麗の僧慧慈、
慧聡のために創建されたと伝えられています。
その後、久しく荒廃していましたが、慈恵大師良源上人が復興、念仏の道場としました。
恵心僧都も入寺、修業されたところから次第に栄えるようになりました。
鎌倉時代の正中2年(1325)に入寺された恵鎮(円観)上人は、
伝教大師が畢生の事業として提唱された大乗円頓戒を復興、
その後百有余年を経た文明18年(1486)に真盛上人が入寺されるに至り、
堂塔と教法を再興、不断念仏の道場とされました。
以来全国に約四百余りの末寺を有する総本山となりました。
<紅葉>
紅葉(こうよう)は、一般的に、落葉広葉樹の葉が、赤や黄色に色づくことを言います。
木の葉が紅くなることを「紅葉」、黄色くなることを「黄葉」と区別することもありますが、
両方含めた意味で「紅葉(こうよう)」が使われることも多いです。
一方、紅葉(もみじ)は、広い意味の紅葉(こうよう)の中で、
楓の葉が紅く色づいた(ひときわ紅色の目立つ)ものが、
紅葉(もみじ)だそうです。
   
※久しぶりにリフレッシュできました!
|

西教寺(山門) |
信長の比叡山焼討ちの際(1571)に炎上。
その直後に築かれた坂本城の城主
となった明智光秀は西教寺の檀徒となり、
復興に大きく力を注ぎます。
天正10年(1582)にこの世を去った光秀は、
6年前に亡くなった内室熙子や
一族の墓とともに境内の片隅に
ひっそりと眠っています。 |

西教寺(本堂) |
総欅入母屋造。
江戸時代 元文4年(1739)に上棟落成。
用材は紀州徳川家からの寄進、
正面の欄間(十六羅漢)や
須弥壇はすべて欅の素木造で
江戸初期の特色を表す豪華な
装飾が施されています。
|

西教寺(大本坊) |
この庭園は裏山の急傾斜の
山畔部を巧みに利用し、
丸刈角刈の小刈込を駆使した観賞庭園

客殿庭園(小堀遠州作) |

盛安寺(穴太の石積み) |
穴太(あのう)の里の盛安寺
穴太積みは、穴太の石工集団が積んだ
石垣のことを云いますが、
自然石を積み上げる野面積みです。
 |

盛安寺(本堂) |
天智天皇の勅願によって建てられた
崇福寺伝来の十一面観音像は平安時代の作。
十一面観音には、珍しい四臂の像で、
第一手は合掌し、左の第二手は錫杖を、
右の第二手は蓮華を持っています。
 |

滋賀院門跡 |
江戸時代末まで天台座主となった
皇族代々の居所であったため
高い格式を誇り、
滋賀院門跡と呼ばれます。

滋賀院庭園(小堀遠州作) |